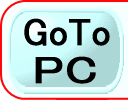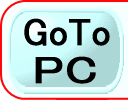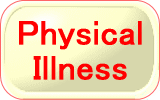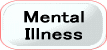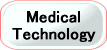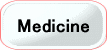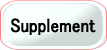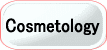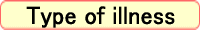|
糖尿病は、血液中のブドウ糖の量、血糖値が慢性的に高くなる病気です。
血糖値は、膵臓のβ細胞から分泌されるホルモンのインスリンによってコントロールされますが、このホルモンの分泌量が不足したり、その働きが低下することによって上昇します。
血糖値がよほど高くならないと自覚症状はでませんが、高血糖になると、のどの渇き、倦怠感、尿量の増加、強い空腹感などの症状がでます。糖尿病自体よりも、それによる合併症である、動脈硬化、心筋梗塞、脳梗塞などが問題です。
|
|
血液中の脂質には、コレステロール、中性脂肪、リン脂質、および遊離脂肪酸という4つの脂質があります。
コレステロールと中世脂肪の量は健康上重要で、これら二つの脂質が多くなりすぎた状態が高脂血症です。
コレステロールが多すぎるときは高コレステロール血症といい、中性脂肪が多すぎるときは高トリグリセリド血症とも呼ばれます。
高脂血症は軽症の段階では自覚症状はでませんが、重症になると動脈硬化の最大の危険因子となります。動脈硬化は、心筋梗塞、脳梗塞の最大の原因です。
|
|
体脂肪が過剰に増加した状態が肥満で、これには、皮下脂肪型肥満と内臓脂肪型肥満の二つのタイプがあります。
皮下脂肪型肥満は、皮膚の下に脂肪が付き、体重の増加が骨や関節に負担を掛けます。内臓脂肪型肥満は高血圧や糖尿病などの生活習慣病の原因となり、問題となります。
|
|
痩せ症は、神経性食欲不振症とか摂食障害、神経性無食欲症などの呼び方もされる、多分に精神疾患的要素を持つ病気です。
痩せ症には、このような精神疾患性のものではなく、何らかの肉体的疾患があって、それが原因で痩せる場合があります。糖尿病やバセドウ病がその典型的な例となります。
|
|
血液中の尿酸量が増加し、血清尿酸値が7.0mg/dL 以上となった状態を高尿酸血症といいます。
この状態が長期間続くと尿酸が体内に蓄積し、関節などに徐々に沈積します。そして、突然、足の親指の付け根が激痛とともに腫れあがり発熱する発作が起こります。
これがいわゆる痛風の発作で、激痛のため、立ち上がったり歩くことも出来なくなるほどです。
|
|
甲状腺の機能に異常がなく、バセドウ病や慢性甲状腺炎や腫瘍、ホルモン合成障害など特別な原因がないのに、甲状腺が大きく腫れあがる病気です。
若い人に多く発生するものの、通常は自然治癒するので経過を見守る程度で済みます。
|
|
甲状腺ホルモンを製造する器官である甲状腺の働きが異常に高まり、血液中の甲状腺ホルモンが過剰な状態になる病気です。
甲状腺ホルモンは体の新陳代謝を促進するホルモンなので、これが増加すると代謝速度が高まり、動悸、頻脈、発汗、食欲が増加するが体重減少、いらいら、不眠などさまざまな全身症状が現れます。
|
|
甲状腺機能低下は、何らかの原因で甲状腺ホルモンの量が減少するために、全身のさまざまな器官に不調がでてくる病気です。
甲状腺ホルモンが低下すると、顔の腫れ、皮膚の乾燥、声が低くなる、便秘、手足のむくみ、全身のだるさなどの症状が現れます。
|
|
副腎皮質の球状層細胞から分泌されるアルドステロンという、血液中の塩分(ナトリウム)の量を調節をするホルモンが過剰になり、高血圧や手足の麻痺を引き起こす病気です。
重度になると、血液中のカリウムが減少する低カリウム血症などが誘引され、高血圧や手足の麻痺、筋力低下、多飲多尿などの症状が現れます。
|