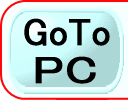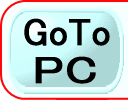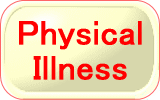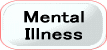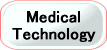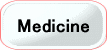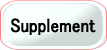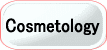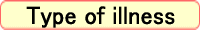|
〔癌〕や〔肉腫〕〔液性がん〕などのそれぞれの言葉は、悪性の新生物である点に変わりはありませんが、それが発生する身体部位などの違いに対応して区別されています。
もともと〔癌〕という医学用語は、人間の皮膚表面や胃腸などの内臓表面壁などの上皮細胞からできた悪性腫瘍のことを指しますので、心臓や骨、血液などのように上皮細胞を持たない部位にこの〔癌〕ができることはありません。
血管や神経や筋肉にできた悪性腫瘍は、一般に〔肉腫〕と呼びますが、極めて稀なことながら心臓や血管にも〔肉腫〕ができることはあります。
心臓や血管にできた悪性腫瘍として〔血管肉腫〕や〔横紋筋肉腫〕などがあります。
また、このような心臓や血管にできる腫瘍の他にも、身体の他の部位で発生した悪性腫瘍が転移した腫瘍ができることもあります。
余談ながら、心臓や血管に腫瘍ができることが極めて稀である理由は二つあります。
一つ目は、心臓を構成する細胞の特殊性です。
他の臓器の細胞では細胞分裂により増殖しますが、心臓の細胞は増殖しないので、がん細胞も増殖できないのです。
また、二つ目は、心臓での発熱量にあります。
心臓自体の重量は体重の0.5%しかありませんが、盛んに血液を送り出すために身体発熱量の10%ほどを占めていて常時40度C近い高温となり、高熱に弱い〔がん〕は死滅してしまうのです。
|