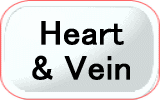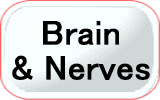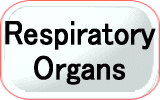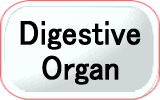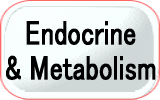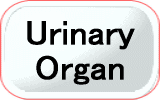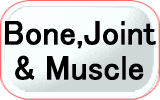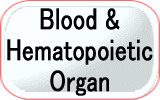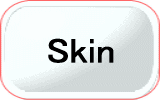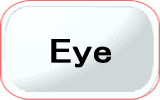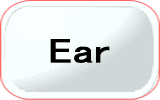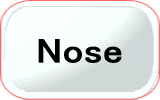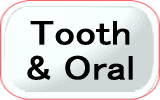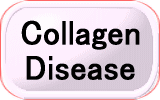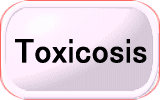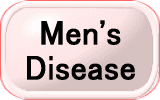|
住血吸虫症には、次のような5つの種類があります。
- 尿路住血吸虫症に属する、ビルハルツ住血吸虫症
- 腸管住血吸虫症に属する、マンソン住血吸虫症
- 日本住血吸虫症
- メコン住血吸虫症
- インターカラーツム住血吸虫症
日本住血吸虫は、虫卵から成虫になるまでに、ミラシジウム、スポロシスト、セルカリアというように姿を変えて成長します。中間宿主のミヤイリガイ体内でセルカリアという段階の幼虫になり、これがヒトの皮膚から侵入して感染します。
この虫は、感染すると、小腸から肝臓へと向かう門脈という血管内に棲息し赤血球を食べ、40日ほどで成虫になり産卵します。オスは常にメスを抱きかかえています。
虫卵は、腸管内や肝臓、脳などに運ばれます。腸管に運ばれたものは便とともに体外に排泄されます。肝臓内では細い末梢門脈枝を通過できないために、門脈枝を閉塞し炎症を起こします。その結果、循環障害や炎症反応、アレルギー反応などを引き起こします。
日本住血吸虫の潜伏期間は、2~3週間で、この時期を経過すると、倦怠感や食欲不振、腹部違和感などの症状が初発します。侵入したセルカリアの数や生育状態、産卵部位などで症状は異なります。
このように日本住血吸虫が重篤な症状を引き起こすのは、成体が腸の細血管で産卵した卵の一部が血流に乗って流出し、肝臓や脳の血管を塞栓することによるところが大きいのです。
感染後の症状は、「侵入期」「急性期」および「慢性期」の三段階を呈して現れます。
日本住血吸虫症は、かつては、山梨県や筑後川流域などで流行していましたが、1978年以降は新たな患者の発生はなく、絶滅したと考えられています。
|